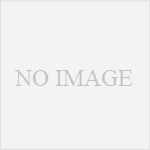あぁ、本当にいなくなってしまうの?
そう彼女は尋ねた。
…ん、うん
彼女の瞳には夕日以外の何かが映り、そして輝いていた。
彼は何か言いたげだったがぐっとがまんしてわずかに微笑した。
でも君には夢があるんだろう?
たとえ俺がいなくなったって君ならその夢を追いかけて実現する能力があるんだ、大丈夫だよ。
そういう問題じゃないょ。。。
もう声は消えかかっていた。
彼女の目から小さなダイヤモンドのような悲しみがほつほつと流れ出した。
抑えようとしているのにもうこらえきれなかった。
どうして私たちは別々の人生を歩まねばならないの?
あなたにとって私は必要のない存在なの?
何か言ってよ…真実のコトを。
こんなにもお互いの心は求めあっているじゃない?
道が違う?
確かにそうかもしれない。
でもだからといって支えあえないわけじゃあないんでしょう?
しかし彼女の心は自ら意見を衝突させていた。
自分の人生はこうあるべきなの。
だからこんなところで恋にかまけている暇や余裕はないんだわ。
ここでこうしているうちに世界のあなたのライバルは
今日も一生懸命真理の探究に精力をついやしているのよ。
第一、いま彼と一緒になってもどうせ一時的な恋。
一時だけの無責任な愛を求めるなんて道徳的に問題だ。
彼がきずつくことや自分が遊ばれるのという結論を望むなんてどうかしててよ。
自分の中でもう限界だった。
この議論は昔から彼女の中で繰り返されてきた。
そしていつも恋をあきらめるという選択肢か恋から逃げるという手段で自分をごまかし続けてきた。
将来最後に一緒になるはずの人に失礼だからなどときれいごとを言い訳にして。
もうそれも限界だった。
彼とすべてを共有したい。
ほんの短い期間でいいからぬくもりをわかちあいたい。
その気持ちが彼女を大胆にしていた。
彼は困ってしまった。
一体どうしてこんなに泣きじゃくるんだろう。
俺が泣かせたみたいじゃないか。
おれのことが好きなら好きだって言ってしまえばいいのに。
何も言わないで俺に決断をせまるなんてちょっとずるいぞ。
いや、それとも言ってはいけないと思って遠慮してるのか?
それとも思っているよりも引っ込み思案なのだろうか。
自分は確かに彼女のことが好きなんだけれども、
ここで彼女と約束を交わしてしまうほどまでよく相手を知らない。
遊びでならもちろん付き合ってやってもいい。
しかし、この純粋で素直な冒涜してはいけないような清純な娘を軽々しく誘っていけない気がしてためらった。
確かに自分は昔の恋人と数か月前に別れたばかりである。
この子が自分の目の前に現れるか現れないかくらいの時期だった。
別にこの子と遊びにいくくらいならいいか、そう思った。
すると今度は彼女が実際に自分と両思いなのかじわじわ不安になってきた。
どうする?!
彼女は今や心配そうな俺の目を下から悲しげにのぞきこんでいた。
何か言ってくださいといわんばかりだ。
俺には彼女が告ってほしいといっているのか、側から離れないと言わせたいように見えた。
彼女はとうとうあきあらめたのか、
先輩、あの私…先輩のことが…
いえ、なんでもないです。。。
そう言って彼女はほおを赤らめると無理してにっこり笑った。
とっても楽しかったです。
たくさんご面倒をおかけしたりはしましたけれど、先輩にも何か私がいたことでプラスになることがあったらいいなって思います。
どうもありがとうございました。
深々と頭を下げると彼女はきびすを返して走るように去って行った。
焦る気持ちの裏に俺はふとわざといぢわるがしてみたくなった。
彼女の名前を呼んで追いかけた。
彼女の姿は見えなかったが、ちょっと鼻をすする音と、小刻みに震える影が彼女の居場所をくっきりと教えてくれていた。
俺はその柱の陰にいって彼女の肩に手をおいて言った
何か俺に言いたいことがあるんだろう、言ってごらんよ。
そのちょっといぢわるな目つきに彼女は聞こえない悲鳴を上げていた。
それは悲痛そうな困惑した彼女の顔からも読み取れた。
あっっ、そ、その。。。
彼女はほんとうに困惑していた。
自分から告白したら彼に体を弄ばれるんじゃないかという不安が彼女を揺さぶった。
相手が惚れた弱みを持っていたら自分は大切にかわいがってもらえるだろうが、
自分に惚れた弱みがあったらつけこまれるという固定観念にしばりつけられていたのだ。
でもここで言わなかったらもう彼と話す機会はないだろう。
また沈黙が流れた。
彼はかわいそうになって彼女をほっと抱きしめた。
彼女は信じられないといった顔をしてからうれしそうに彼の胸に顔をうずめた。
誰かの足音がこちらにやってくる音がした。
今週の日曜日空けておいてくださいね。
それだけ言うと彼は立ち去った。
残された彼女は振り向きざまの彼に見えるように懸命にうなずいた。
これが彼にとって大学生活最後のもっとも心に残る恋愛の序章となったのである。
彼女はぼーっと立ち続けていたが
やがてやってきた教授にあいさつだけすると幸せで胸がいっぱいになって跳ねるようにして家に帰った。
彼の方は卒業式後の打ち上げに参加しながら、いったい全体なんであんな大胆なことをしてしまったんだろうとか、彼女はやっぱり俺のことが好きにちがいないと思うにつけて胸が高鳴り、何もかもがうわの空だった。